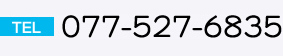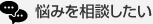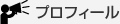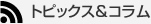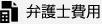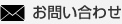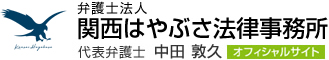弁護士法人 関西はやぶさ法律事務所
〒520-0051 大津市梅林1丁目15番30号 林ビル本店2階
(JR東海道本線「大津」駅より県庁方面に徒歩5分)
※当事務所にはお客様専用駐車場がございますので、地図等をご参照の上、ご利用下さい。

群衆心理
『フランスの社会心理学者ル・ボンは「群衆心理」という著書で、次のように述べている。
「群衆の最も大きな特色は次の点にある。それを構成する個々の人間の種類を問わず、また、彼らの生活様式や職業や性格や知能の異同を問わず、その個人個人が集まって群衆になったというだけで集団精神を持つようになり、そのおかげで、個人でいるのとはまったく別の感じ方や考え方や行動をする」
そして群衆の特色を、彼は鋭く定義しているー衝動的で、動揺しやすく、昂奮しやすく、暗示を受けやすく、物事を軽々しく信じる、と。そして群衆の感性は誇張的で、単純であり、偏狭さと横暴さと保守的傾向を持っている、と。
昭和15年から昭和16年12月の開戦(太平洋戦争)への道程における日本人の、新しい戦争を期待する国民感情の流れとは、ル・ボンのいうそのままの姿と言っていいような気がする。
それもときの政府や軍部が冷静な計算で操作していったというようなものではない。日本にはヒトラーのような独裁者もいなかったし、強力で狡猾なファシストもいなかった。民衆と不可分の形でリーダーも群衆のひとりであり、民衆のうちにある感情を受容し反映する場合にのみ、リーダーは民衆を左右できたのである。』
以上は、半藤一利氏著「歴史探偵昭和史をゆく」(PHP文庫)からの抜粋です。
あれから約70年の年月を国民は過ごしてきました。戦後は、少なくとも日本は平和な状態を維持してきました。
しかし、その平和は国民自身が不断の努力をもって維持してきたものでしょうか?大東亜戦争の敗戦について、その原因分析や議論を充分に行って、国民自身が成長したから平和が維持されているのでしょうか?
もっと言えば、現在の日本国民が、大東亜戦争勃発の頃と同じような状況に置かれることになったときに、あの頃と違って冷静で合理的な世論を形成し、政府を平和裡に突き動かすことができるのでしょうか?私見ではありますが、甚だ疑問に思う今日この頃です。
やはり悲惨な時代、負け戦の時代には目を向けたくないという日本人は少なくないのではないでしょうか?
そして、日本の「侵略戦争」がいけなかった。ここは「反省」「謝罪」しなければならない、ということで片づけてしまい、結局その頃に何が起こっていたのかについて、詳しく知ることを避けている日本人は少なくないのではないでしょうか?
いや、また脈絡もないよもやま話を書いてしまいました。いや半藤一利氏の著書のことじゃありませんよ。私の記述部分のことですよ。半藤氏の著書はどれもすばらしいです。
望ましい弁護士の選び方
最近、何人もの弁護士に法律相談したが、どの弁護士も違うことを言うので、どの弁護士が言っていることが正しいのか分からなくなったと言って、私にも同じ相談をしてこられる相談者の方が増えてきました。どの弁護士の言っていることが正しいのかと言えば、結論から言うとどの弁護士の言っていることも間違いではない。つまり、やはりどれも正解なのだと思われます。
ただ、到達する結論は、たぶんひとつしかないはずですが、そこへ至る方法論が、各弁護士によって異なるのだと思います。
例えば、難しい法律問題をはらんでいる事案や事実認定や評価がどちらに転んでもおかしくない事案や自分の依頼者の主張の立証が出来るのかどうか微妙な場合に、それを楽天的に考える弁護士もおれば、厳しめに考える弁護士もいます。そういう場合に、一旦内容証明郵便送付によって、相手方の反応を見ようとする弁護士もおれば、いきなり訴訟に打って出れば手っ取り早いと考える弁護士もいるでしょう。あるいは、調停で話し合いをすればよいのではないかと考える弁護士もいるでしょう。これらの方法はいずれも間違ってはおりません。
結局、どういうタイプの弁護士に自分の事件を依頼するかは、弁護士の出してくるアドバイスが、自分の感覚にどれだけ合致しているのかによるのだと思います。
仮に弁護士が、訴訟をやるのが妥当だとアドバイスをして、それが、あなたの感覚にしっくりと来るのであれば、あなたは、その弁護士に自分の事件を依頼をすべきなのだと思います。弁護士費用が安いからと言って、あるいは敏腕弁護士との噂があるからと言って、自分の感覚にしっくり来ない法的手段をとろうとする弁護士に依頼するのは、結局、あなたが最終的に納得のいかない結果になる危険性が高くなると思います。
弁護士をやってると人間不信になる?
私はよくお客さんから、「弁護士なんて仕事をしていると人間不信になりませんか?」という質問をよく受けます。それに対しする私の答えは、「とんでもない、かえって人間の人間らしさを再認識し、より人間に対して興味を持ちます。」というものです。
そもそもそういう質問をされるお客さんは、紛争が生じるのは、そもそも当事者のどちらかが嘘をついているからであろうと思っておられるようです。確かに、紛争の中には、当事者のどちらか一方が大嘘をついていて、他方の当事者からの請求を逃れたり、他方の当事者に対して不当な請求を行おうとするものも見受けられます。しかし、裁判所でつき通せるような嘘というものはなかなかありません。裁判において、ほとんどの嘘は、矛盾を露呈し、化けの皮がはがれてしまうものです。どうせばれる嘘をついている人を法廷で見ると滑稽でもあります。
それはさておき紛争が起こる基本的なメカニズムは、ひとつまたは複数の出来事・事象その他に対する当事者の解釈・認識の違いにあります。誰も嘘はついていなくても、当事者双方の解釈・認識の違いによって、紛争はどんどん起こってくるのです。
たとえば、自動車同士の交通事故において、被害者Xが、自分の乗っていた被害車両は新車だったんだ、壊れた部分の修理には、多岐にわたる部品の交換や、修理部分とその他の部分の色の違いが出るのは嫌だから車両全体の塗装のやり直しが必要なんだと主張したとしましょう。加害者Yとしては、当然、そこまでの部品交換は必要ないし、車両の一部を破損しただけなので車両全体の塗装のやり直しまでは必要ないだろうと反論するでしょう。この事案においては、誰もうそをついていません。ただ被害車両の修理の程度について、当事者双方の認識や解釈が異なるだけです。
紛争の多くは、このようにして、誰もうそをついていなくても、出来事・事象その他に対する認識・解釈の違いにより生じてきているのです。物事を自分のいい方に解釈したいというか、してしまうのが、人間の性なのです。
しかしまた、人間には、お互い折り合いをつけて、社会において平穏に共同生活をしてゆこうという知恵もあるのです。前記の交通事故の例をとっても、X氏、Y氏が双方譲り合って、示談が成立することも大いにあり得ることでしょう。その紛争解決のお手伝いをいをするのが弁護士であったり、裁判所であったりするわけです。
ですから、弁護士をやっていても、人間不信にはなりませんし、むしろ人間の人間らしさに対するいとおしさが深まるケースだってあるのです。
顧問弁護士の有用性について
顧問弁護士とは会社あるいは個人にとってどんなメリットがあるのでしょう?顧問弁護士は、会社や個人の顧客と顧問契約を結んだ弁護士のことを言いますが、顧問弁護士は顧問先の営業や組織について詳しく把握することになりますので、何かトラブルが起こりそうな点についてアドバイスを行い、顧問先のトラブルを未然に防止することが出来ます。また、何か法的な疑問点やトラブルが生じた場合には、顧問先は電話1本あるいはファックス1本で法的な疑問点やトラブルの解決法を顧問弁護士に問い合わせることが出来ます。必要であれば顧問弁護士と面談し法律相談に応じてもらうことも当然可能です。また、顧問先は契約書のサンプルの入手、あるいは契約書の作成、作成した契約書のリーガルチェックを顧問弁護士を利用することによって容易に行うことが出来ます。
さらには不幸にも顧問先が法的にトラブルに巻き込まれ、またトラブルを起こしてしまい当事者間では解決不可能な状態に陥ってしまった場合でも、顧問弁護士がいれば即座にその処理を依頼し、顧問先の代理人としてトラブルの解決にあたらせることも可能となります。顧問弁護士は顧問先の代理人としてトラブル解決の交渉にあたり、必要であれば訴訟を提起したり、提起された訴訟に応訴したりします。
高度に複雑化した現代社会においては、顧問弁護士を有しているかいないかにより、会社や個人の将来的方向性が大きく違ってくることもあります。かかる弁護士を有している会社や個人の方が法律的に賢明な方向性を選択でき、その利益を守る良好な方向性を維持できることはいうまでもありません。
顧問料といっても会社や個人の規模によってさまざまな料金設定が可能であり、リーズナブルな顧問料で顧問弁護士を利用することも可能です。顧問弁護士を利用されていない会社や個人の方には、この機会に顧問弁護士活用の検討をお勧めいたします。
医師と弁護士はよく並べて言われるが・・・
医師と弁護士はよく並べて論じられることがあります。身体の病を診察し治療するのが医師だとすれば、トラブルを洞察し事件解決に導くのが弁護士ですから、ある意味共通項があるのかもしれません。
しかし、私はあるひとつの経済的観点から見た場合、医師と弁護士は大いに異なるものだと思うのです。それは医師には診療報酬制度があって、患者は2割や3割の安い医療費の負担で治療を受けることが出来ます。しかし弁護士にはこういう制度はなく、弁護士は事件処理に要する労力分の着手金及び勝訴した場合の報酬金全額を依頼者に請求しなければなりません。依頼者はかかる着手金や報酬金を全額負担することになります。
弁護士費用を一時的に立て替えて支払ってくれる法律扶助制度もありますが必ずしもまだ充分とは言えません。今後弁護士が市民にとってより利用しやすい存在となるためには、弁護士の努力のみならず法律扶助制度等の拡充は必須の前提となることでしょう。
弁護士は正義の味方か?
弁護士は正義の味方か?と問われたら、弁護士はどう答えるのでしょう?私がこのような質問を受けたとすれば、「正義とはどういう意味か明確にしてもらわなければ答えられません。」という答えになると思われます。依頼者の利益を守るのが正義と考える弁護士もいれば、法律を守るのが正義と考える弁護士もいるでしょう。私にしてみれば、法律で認められる範囲内で依頼者の利益を最大限に守ることが正義だと考えています。たとえば依頼者の利益を追求するあまり、虚偽の証拠をそうと知りつつ(気づきつつ)裁判所に提出することは、正義とは言えないと思います。結論として、私は「私なりに解釈する正義の味方である。」ということになります。
かかる私なりに考える正義を守るために、ときとして依頼者の方には歯がゆい思いをさせてしまうこともあります。すなわち依頼者の意向ならばどのような行為も行うというわけにもいかないわけです。他の弁護士もそれぞれの解釈する正義のために法律業務を行っていることでしょう。このあたりは弁護士業は普通のサービス業とは少しだけ異なるのかもしれません。
弁護士の日常業務の様子
弁護士の日常業務はというと、端的に言って地味です。だいたい私は、朝は10時ころに事務所に出て、夜の8時か9時ころまで仕事をします。たとえばある一日の私のスケジュールは、こんな感じ・・・午前10時30分から昼まで依頼者と打ち合わせ、午後1時15分から裁判所で裁判に出廷、午後3時から5時まで別の依頼者と打ち合わせ、それ以外の時間帯は、事務所で電話を受けているか、かけているか、書面を作成しているか、文献・判例を調べているか・・・まあそんなところで、テレビドラマに出てくるなんとか弁護士と比べると恐ろしく地味であります。
さすがに尋問とかになれば、相手方証人の反対尋問を行い、その証言の矛盾点をつき、証言の信用性を崩してしまう爽快な場面もありますが、民事事件の証人尋問だと、いかに爽快に相手方証人の証言の信用性が崩れ去ったか、一般の人には分からなかったりします。そういう意味からも弁護士の業務で華々しいと言える部分はほとんどないかもしれないのですが、日々こつこつと依頼者及び法律のために働き続けるのが弁護士なのです。