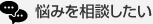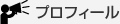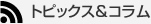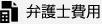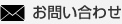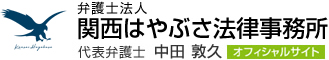弁護士法人 関西はやぶさ法律事務所
〒520-0051 大津市梅林1丁目15番30号 林ビル本店2階
(JR東海道本線「大津」駅より県庁方面に徒歩5分)
※当事務所にはお客様専用駐車場がございますので、地図等をご参照の上、ご利用下さい。

遺言について
民法の定める遺言方式には、普通方式と特別方式がありますが、一般的な普通方式について説明することにします。普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。他人に真似の難しい遺言者の筆跡によって、その終意を確保しようというのがその趣旨です。自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつその変更の場所に印を押さなければ効力がありません。
遺言書の全文は遺言者が自筆しなければなりませんが、意思が正確に示されれば、表現のしかたは問われません。文字は外国語、略字、速記文字などでもよいのですが、タイプライター、ワープロ等を用いたもの及びテープレコーダーに吹き込んだものは自筆証書とはなりません。
作成年月日の確定できない遺言書は無効です。また年月だけで日付の記載のないものも無効です。日付は、必ずしも暦日であることを要せず、「第何回誕生日」とかのように、正確に年月日を確定しうる表示であれば差し支えありませんが、何年何月吉日というのは、暦日を特定できないので日付のないものと判断されます。
氏名の記載は、遺言者の同一性を確認し、他者から区別できる程度のものである必要がありますが、氏と名を併せて書かなくても、氏または名だけでも同一性を示す場合は、有効であり、雅号・通称・芸名・ペンネームでも同様に有効と解されます。
押印に関しては、まず遺言者自身の印であることが必要ですが、実印でなくても認印でも拇印でもよいです。
公正証書遺言
2人以上の証人の立ち会いを得て遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後各自署名押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印する方式をとる遺言を公正証書遺言といいます。
必ずしも公証人役場で作成する必要はなく、公証人の出張を求めて病床で作成することもできます。なお、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記し、署名に代えることができます。
秘密証書遺言
遺言者が、遺言者または第三者の書いた遺言書に署名押印し、その証書を封じて証書に用いた印章で封印し、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出し、自分の遺言書である旨、また遺言書が他人によって書かれているときは、筆記者の氏名・住所を申述し、次に公証人が封紙に証書を提出した日付および遺言者の申述を記載し、そのあと遺言者・証人・公証人が、封紙に署名押印するという方式の遺言を秘密証書遺言といいます。
遺言書は、遺言者が署名押印したものであればよく、筆記者・筆記の方法(ワープロ書き等)は問題にならないと解されています。加除・変更の形式は、自筆証書遺言と同様です。遺言書の印と封印に用いた印が違っていれば無効です。
3つの方式の長短
自筆証書遺言は作成手続が簡単であり、遺言の存在そのものを秘密に出来るし、費用もかからないという長所がありますが、遺言書の滅失・偽造・変造・隠匿のおそれがあり、検認が必要であるという短所もあります。方式違背や内容不明のため遺言が無効になる危険性もあります。
公正証書遺言は、遺言の存在と内容が明確であり、証書原本は公証人役場に保存されるので滅失・偽造・変造・隠匿のおそれがなく、遺言の効力が争われる危険も少なく、遺言の執行に検認を受ける必要もない長所がありますが、存在や内容を秘密にできないし、手続きが複雑で費用もかかる短所があります。
秘密証書遺言は、内容を秘密にしておくことができるが、手続が複雑なわりに、公証人役場で保存しないので、滅失・隠匿のおそれがあり、費用もかかり、検認が必要という短所があります。また、遺言の効力を争われる危険性も低くはありません。
遺言書の有効性について後日の紛争を一番回避しやすい点から考えて、費用がかかるなどの短所はありますが、公正証書遺言がお勧めでしょう。
検認とは
公正証書以外のすべての方式の遺言について、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡後遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。
検認は、遺言書の形式・態様などを調査・確認して、その偽造・変造を防止し、保存を確実にする目的でなされる一種の検証手続きです。いわば証拠保全手続きですから、遺言書の現状をありのまま確認するだけで、遺言内容の真否・有効無効を判定するものではありません。したがって検認を経た遺言書の効力を争うことはもちろん可能です。
相続その2ー相続放棄・限定承認・単純承認について
被相続人の死亡により相続が開始すると、相続人は被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。しかし、相続財産の中には、不動産などのプラスの財産もあれば、借金のようなマイナスの財産もあります。
したがって、債務が積極財産を上回るケースもあり、この場合にも相続人にこれらの権利義務すべてを承継させると酷な結果となります。また、積極財産の方が債務より多くても、相続することについて潔しとしない人がいるかも知れません。
そこで民法は、相続の放棄と承認の制度を設け、相続人に対して、被相続人の権利義務を承継するか、あるいは拒否するかの選択権を与えました。①相続放棄とは、相続による権利義務の承継を拒否することです。
相続の承認には、②条件をつけずに全面的に被相続人の権利義務の承継を認める単純承認と、③被相続人の債務は、相続によって得た財産を限度としてのみ責任を負い、相続人の固有財産をもっては責任を負わないという限定承認、の2種類があります。
相続放棄
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする方法によって行います。
この3ヶ月の期間は熟慮期間と呼ばれ、この間に、相続人が被相続人の財産関係を調査してその内容を把握し、相続放棄等をするべきかを検討するのです。3ヶ月の期間だけでは相続財産の調査が完了しない等の事情がある場合には、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申請することも出来ます。なお、相続人が数人あるときは、熟慮期間は、各相続人ごとに進行します。
相続放棄は、家庭裁判所への申述という方式によってしなければなりません。相続放棄をしようとする者は、被相続人の住所地または相続開始地の家庭裁判所に対して、「相続放棄申述書」を提出する方法により行います。この申述が受理された場合、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を出してもらい、相続債権者からの請求に際しては、右証明書を提示するなどして、その支払いを拒否することになります。
相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人でなかったものと見なされます。
したがって、たとえば被相続人の子らが全員相続放棄をした場合、それまで相続人でなかったはずの、直系尊属、あるいは兄弟姉妹やその代襲者が相続人となる場合がありますので、これらの者に対する配慮も必要となります。
限定承認
限定承認は、相続財産の限度でのみ被相続人の債務や遺贈について責任を負うという限定つきで行う相続の承認です。
相続人が限定承認をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、財産目録を調製して、相続人全員で家庭裁判所に対して限定承認をする旨の申述をしなければなりません。したがって、相続人の中に限定承認に反対する者があれば、他の相続人も限定承認をすることが出来ません。
限定承認をした場合、相続財産の管理と清算手続を行わなければなりません。一般的には、家庭裁判所が財産管理人を選任し、その者が相続人全員に代わって、相続財産の管理と清算手続を行います。
単純承認
被相続人の権利義務の承継に関して、何の留保もつけずに全面的に被相続人の権利義務の承継を承認する単純承認の場合、家庭裁判所への申述は特に必要ありません。ただし、民法は、法定相続人の単純承認の意思表示がない場合にも、一定の事由があれば、単純承認をしたものと見なす法定単純承認という規定を設けています。
法が単純承認と見なすのは、相続人が
- 相続財産の全部または一部を処分した場合(ただし保存行為や管理行為は除かれます。)
- 3ヶ月の熟慮期間を徒過した場合
- 相続財産の隠匿・消費などの背信行為をした場合です。
相続その1ー相続人・相続分・遺留分について
相続人となるのは誰か
人が死亡すれば相続が開始します。被相続人の権利義務を承継するのが相続人です。相続人は、誰なのかが問題となります。
民法の定める相続人とその順位は、以下のとおりです。
- 第1順位 子(養子や、代襲相続人たとえば孫なども含む)
- 第2順位 直系尊属(たとえば被相続人の親)
- 第3順位 兄弟姉妹(代襲相続人のたとえば甥なども含む)
なお、被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
たとえば、被相続人(夫)に妻と子がいれば、相続人は第1順位の子と、常に相続人となる妻が相続人になります。子どもがいなければ、第2順位の直系尊属と、妻が相続人になります。子も直系尊属もいなければ、第3順位の兄弟姉妹と、妻が相続人となります。なお、内縁の妻は相続人には該当しません。
※代襲相続は、相続人である子や兄弟姉妹が
- 相続開始以前に死亡したとき、
- 相続欠格(先順位の相続人を殺して刑に処せられたりした場合など)に該当して相続権を失ったとき、
- 廃除(被相続人を虐待したり、重大な侮辱をくわえたり、その他著しい非行があったとき
に、被相続人の請求によって相続資格を失わせる制度)によって相続権を失ったときに、その者の子がその者に代わって相続する制度です。
法定相続分
遺言による相続分の指定があれば別ですが、特になければ各相続人の相続分は、民法の定める法定相続分によることになります。
1.子と配偶者が相続人である場合
子と配偶者はおのおの2分の1の割合による相続分を有します。
たとえば相続人が妻と子ども3人であれば、妻の相続分は2分の1、子どもらはそれぞれ6分の1の相続分を有します。
2.配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です。たとえば被相続人の両親が健在であれば、両親は、それぞれ6分の1の相続分を有することになります。
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。たとえば、兄弟姉妹が3人いれば、それぞれ12分の1の相続分を有します。
特別受益者の相続分
共同相続人の中に、被相続人から遺贈(遺言による遺産の処分)を受けたり、また結婚とか養子縁組のために、もしくは生計の資本として、生前に贈与を受けた者(特別受益者)がいる場合には、被相続人が相続開始時点において有していた財産の価額にその贈与の価値を加えたものを相続財産と見なし、指定相続分または法定相続分によって算出した相続分の中からその遺贈または贈与の価額を控除し、その残額をもってその特別受益者の相続分とします。
寄与者の相続分
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者(特別寄与者)があるときは、被相続人が相続開始時点において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産と見なし、指定相続分または法定相続分によって算出した相続分に寄与額を加えた額をもってその特別寄与者の相続分とします。
遺留分
遺留分とは、被相続人の財産のうち、最低限相続人に残さなければならない財産の割合で、被相続人が他に贈与等をしても相続人が最低限確保できるものです。
遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の相続人で、その割合は、以下のとおりです。
①直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
②その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
遺留分の算定の基礎となる財産の範囲ですが、これは被相続人が相続開始の時点で有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除したものです。この贈与は、被相続人の死亡前1年間にしたものか、1年以上前でも贈与当事者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたもの、このほか相続人の誰かが婚姻、養子縁組のため、生計の資本として受けた贈与も含みます。
遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している者に対して遺留分減殺請求を行使することが出来ます。行使の方法は特に定められていませんが、明確な証拠を残すという意味で内容証明郵便によって行使するのが通常です。遺留分減殺請求の家事調停を申し立てる方法もあるでしょうし、訴訟によって遺留分減殺請求を行いこれに基づく請求を行うのでもかまいません。
なお、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始と減殺すべき贈与等があったことを知ったときから1年以内に、相続開始の時から10年以内に行使しなければなりません。